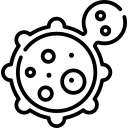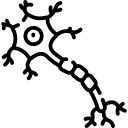診療科目
MEDICAL SUBJECTS
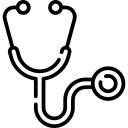
一般内科(総合診療科)
小動物の一般内科(総合診療科)は、犬や猫などのペットに起こる幅広い内科的な病気の診断・治療・管理を行う、いわば「かかりつけ医」のような分野です。
症状の原因がはっきりしない場合や、複数の臓器に関わる病気にも対応します。
主な診療内容
| 分野 | 主な内容 |
|---|---|
| 呼吸器 | 咳、くしゃみ、鼻水、呼吸困難 など |
| 神経系 | けいれん、ふらつき、意識障害 など |
| 消化器 | 嘔吐、下痢、食欲不振、便秘 など |
| 心臓・循環器 | 心雑音、咳、運動不耐性、失神 など |
| 腎泌尿器 | 頻尿、血尿、おしっこが出ない など |
| 内分泌・代謝 | 糖尿病、副腎疾患、甲状腺機能異常 など |
| 血液・免疫 | 貧血、出血傾向、自己免疫疾患など |
| 感染症 | ウイルス、細菌、真菌などによる疾患 |
主な検査
- 一般身体検査(聴診・触診・視診など)
- 血液検査・尿検査・便検査
- レントゲン・超音波検査
- 内視鏡検査(消化器など)
- ホルモン検査、感染症検査
目的
- 全身状態の把握
- 症状の原因特定と治療
- 病気の予防と早期発見
- 高齢動物の健康管理(シニアケア)
こんなときに受診
- なんとなく元気がない
- 食欲が落ちた、体重が減った
- 咳や吐き気、下痢が続く
- 定期健診や健康診断をしたい
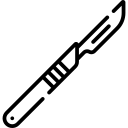
一般外科(軟部外科)
一般外科(軟部外科)が対応する主な分野
- 一般外科
- 去勢・避妊手術(不妊手術)
- 異物摘出(飲み込んだおもちゃなど)
- 帝王切開、ヘルニア整復など
- 軟部外科
- 胃腸・肝臓・膀胱などの臓器手術(例:腫瘍摘出、膀胱結石除去)
主な手術の例
- 避妊・去勢手術
- 消化管異物摘出術(誤飲・誤食など)
- 腫瘍摘出術(良性・悪性)
- 子宮蓄膿症手術
- 胆嚢摘出術、膀胱結石摘出
手術の流れ(一般的な例)
- 診察・検査(身体検査、血液検査、レントゲン、エコーなど)
- 術前準備(絶食・麻酔前投薬)
- 全身麻酔下での手術
- 術後管理・入院(当日〜数日)
- 抜糸・経過観察
飼い主様が知っておきたいこと
- 術前検査や麻酔のリスク説明をしっかり聞くこと
- 術後ケア(傷口管理、カラー装着、安静)がとても大事
- 高齢動物や持病のある子は慎重な対応が必要
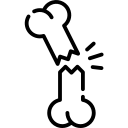
整形外科
主な対象
- 犬や猫(特に犬が多い)
- ウサギや小動物にもみられる
対象となる疾患・ケガ
- 骨折
- 脱臼
- 靱帯損傷(例:前十字靱帯断裂)
- 股関節形成不全
- 膝蓋骨脱臼(パテラ)
- 椎間板ヘルニア
- 成長障害や先天性奇形
- 腫瘍による骨の変形や破壊
主な治療法
- 手術(プレート固定、ピン・スクリュー、人工関節など)
- 保存療法(ギプス・副木、運動制限、内科治療)
- リハビリテーション(レーザー治療なども含む)
治療方法
当院でも専門の先生を招致し、整形外科や脊椎外科の手術も対応可能です。また、対応困難な症例や緊急性を要する場合は、専門の整形外科施設や二次診療施設へ紹介することもございます。
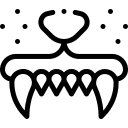
歯科
主な対象動物
- 犬・猫
- うさぎ、モルモット、小型齧歯類などの小動物(特に草食系)も歯のトラブルが非常に多い
主な歯科疾患とトラブル
- 犬・猫に多いもの
- 歯周病(歯肉炎)←最も多い
- 歯石の蓄積・口臭
- 乳歯遺残(特に小型犬)
- 歯の破折・欠損
- 根尖周囲病巣(顔が腫れる)
- 口内炎(特に猫)
- 不正咬合(噛み合わせの異常)
- 口腔内腫瘍
- 小動物(うさぎなどの草食動物)に多いもの
- 歯の過長(伸びすぎ)
- 不正咬合(食欲不振、よだれ、涙目の原因に)
- 口腔内腫瘍(ハリネズミに多い)
主な検査・診断
- 口腔内の視診・触診
- 歯科用レントゲン(歯根や顎骨の状態を確認)
- 麻酔下での歯のスケーリングや検査
- 必要に応じてCT検査(顔面や顎の評価)
主な治療内容
- 歯石除去・スケーリング
- 全身麻酔下で実施
- 超音波スケーラー+研磨(ポリッシング)で歯をきれいに
- 歯周ポケットの洗浄も行う
- 抜歯
- 重度の歯周病、破折、乳歯遺残などに対して
- 麻酔が必要、術後の痛み止めも使用
- 猫の難治性口内炎
- 内科的処置
- 歯肉炎や口内炎には抗菌薬・消炎鎮痛剤・サプリなど
- 猫の難治性口内炎ではステロイドや免疫療法も
- 不正咬合の矯正・カット
- うさぎなどは定期的な歯のケアが必要なこともある
飼い主様ができる予防ケア
- 毎日の歯磨き(子犬・子猫のうちから習慣に)
- 歯磨きシートやデンタルガムの使用
- 定期的な歯科健診(半年〜1年ごと)
- 高齢動物や小型犬は特に要注意!
歯科のポイント
- 犬猫の3歳以上の約8割が歯周病を抱えていると言われる
- 歯周病は心臓・腎臓・肝臓など他の臓器に悪影響を及ぼすことも
- 猫の「口が痛くて食べられない」は口内炎や吸収病変が原因のことも
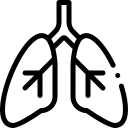
呼吸器科
対象となる主な病気
- 上部気道(鼻・咽喉)
- 鼻炎、慢性鼻炎
- 鼻腔腫瘍
- 軟口蓋過長症(短頭種症候群の一部)
- 鼻腔内腫瘍(高齢動物にみられることが多い)
- 下部気道(気管・気管支・肺)
- 気管虚脱(小型犬に多い)
- 気管支炎(慢性・アレルギー性など)
- 肺炎
- 気胸・肺水腫
- 肺腫瘍
- 胸水貯留(心疾患や腫瘍性疾患などが原因)
主な検査・診断法
- 胸部レントゲン検査
- CT検査(より精密に診断)
- 気管支鏡検査(大学病院や専門科のある診療施設)
- 血液検査・酸素飽和度の測定
- 痰や洗浄液(BAL)の検査による病原体の検出
主な治療法
- 薬物治療(抗生物質、ステロイド、気管支拡張薬など)
- 酸素吸入(急性期管理)
- 手術(腫瘍切除や短頭種症候群の矯正[軟口蓋切除]など)
- ネブライザー治療(吸入療法)
- 胸水や気胸に対するドレナージ処置
特に注意が必要な犬種
- フレンチブルドッグ、パグ、シーズー、ボストンテリアなどの短頭種は、呼吸器トラブルが起きやすい
- 老犬では喉頭麻痺や気管虚脱に注意
飼い主様が知っておくと良いこと
- 「咳が続く」「呼吸が苦しそう」「ゼーゼー・ガーガー音がする」などは受診サイン
- 呼吸困難(舌の色が紫色、開口呼吸[犬以外])は緊急疾患の可能性あり、すぐ病院へ
- 慢性疾患も多く、継続的なケアが必要なことも
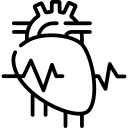
循環器科
対象となる主な臓器・器官
- 心臓(心筋・弁膜・心内膜・心膜など)
- 血管(動脈・静脈)
- 肺循環や体循環に関係する器官
主な対象疾患
- 先天性心疾患(例:心室中隔欠損、動脈管開存症など)
- 後天性心疾患(例:僧帽弁閉鎖不全症[犬]、肥大型心筋症[猫]など)
- 不整脈
- 高血圧
- 心膜疾患(例:心嚢液貯留)
- 肺高血圧症 など
みられる症状
- 咳
- 呼吸困難
- 運動不耐性(疲れやすい)
- 失神
- 腹水や浮腫
- チアノーゼ(舌や歯茎が青紫になる)
主な検査方法
- 聴診(心雑音の確認)
- 心電図(ECG)
- レントゲン(X線)検査
- 心エコー(超音波)検査
- 血圧測定
- 血液検査(心臓バイオマーカーなど)
治療方法
- 内科的治療(投薬:利尿薬、ACE阻害薬、強心薬など)
- 外科的治療(先天性疾患・僧帽弁閉鎖不全症に対する手術など)
- 食事療法
- 生活管理(栄養管理など)
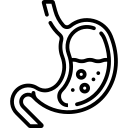
消化器科
主に診る臓器・器官
- 口腔、咽頭、食道
- 胃・小腸・大腸(結腸・直腸)
- 肝臓、胆嚢、膵臓(※肝胆膵科と連携)
- 肛門周囲・肛門腺 など
主な症状と病気
- よくある症状
- 嘔吐(慢性・急性)
- 下痢・血便
- 食欲不振・体重減少
- お腹が痛そう・張っている
- 便秘・うんちが出にくい
- よだれが多い、吐き戻し
- 主な疾患例
- 胃腸系
- 胃炎・腸炎(急性・慢性)
- 異物誤飲による消化管通過障害、中毒
- 炎症性腸疾患(IBD)
- 腫瘍(消化器型リンパ腫、腺癌など)
- 便秘・巨大結腸症(特に猫)
- 直腸脱・肛門周囲疾患
- 肝臓・胆嚢・膵臓系(肝胆膵)
- 胆管肝炎・肝リピドーシス(猫)
- 胆泥症・胆嚢粘液嚢腫
- 膵炎(犬猫ともに多い)
- 膵外分泌不全(EPI)
- 胃腸系
主な検査内容
- 身体検査・聴診・触診
- 血液検査(肝酵素、各種診断マーカーなど)
- 糞便検査
- レントゲン・エコー(超音波)検査
- 内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)
主な治療法
- 対症療法(吐き気止め、整腸剤、下痢止めなど)
- 食事療法(消化器疾患用の療法食)
- 抗生物質やステロイド(IBDなどの免疫関連疾患に)
- 点滴治療(脱水や電解質異常の補正)
- 内視鏡や外科手術(異物除去や腫瘍切除など)
消化器科の役割
- よくある症状(吐く・下痢する)に対応する最前線
- 慢性疾患の長期管理や栄養サポートも担当
- 必要に応じて内視鏡・手術・CT検査などを実施
- 肝胆膵・内分泌・腫瘍科と密接に連携
飼い主様が気をつけたいポイント
- 「ただの吐き気」でも慢性化や深刻な病気の可能性あり
- 「ごはん食べない・痩せる」は消化吸収のトラブルかも
- 慢性の下痢・便秘は腸の病気やホルモン異常のことも
- 誤飲が疑われるときはすぐ受診が鉄則
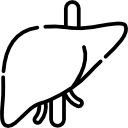
肝・胆・膵科
主な対象臓器
- 肝臓(かんぞう)
- 胆嚢(たんのう)
- 胆管(たんかん)
- 膵臓(すいぞう)
主な病気・症状
- 肝臓
- 肝炎(急性・慢性)
- 肝硬変
- 肝性脳症(アンモニアの蓄積による神経症状)
- 肝リピドーシス(猫に多い脂肪肝)
- 門脈体循環シャント(PSS)
- 肝腫瘍(良性・悪性)
- 肝葉捻転(ウサギ)
- 胆嚢・胆管
- 胆泥症(たんでいしょう)
- 胆嚢粘液嚢腫(胆嚢がゼリー状になる)
- 胆石症
- 胆管閉塞や胆管炎
- 膵臓
- 膵炎(急性・慢性)
- 膵外分泌不全(EPI)
- 膵臓腫瘍(インスリノーマ[フェレットに多い]など)
主な検査
- 血液検査(肝酵素・各種診断マーカー・総胆汁酸などの評価)
- 超音波検査(エコー)
- CTやMRI(詳細な評価や手術前診断)
- 肝臓の生検
- 糞便検査(膵外分泌不全の評価)
主な治療法
- 内科療法(点滴・抗炎症薬・肝保護剤・消化酵素補充・食事療法など)
- 外科治療(胆嚢摘出、シャント血管手術など)
- 食事療法(低脂肪・高消化性などの療法食が重要)
- 入院治療(急性膵炎などは命に関わることも)
飼い主さんが気をつけたい症状
- 食欲不振・元気がない
- 嘔吐・下痢
- 黄疸(粘膜の色・白目が黄色い、尿の色が濃い黄色〜オレンジ色)
- お腹の痛み(背中を丸めている、祈りのポーズ)
- 食べてはいるが痩せてきた、筋肉が落ちた
- 行動がぼーっとしている(肝性脳症の疑い)
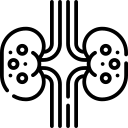
腎泌尿器科
担当する主な臓器・器官
- 腎臓(左右)
- 尿管
- 膀胱
- 尿道
- 前立腺(オスのみ)
主な症状と疾患
- よくある症状
- おしっこの量や回数の異常(多い/少ない)
- 血尿、濁った尿
- トイレに頻繁に行くが出ていない
- 排尿時に鳴く、痛がる
- 水を大量に飲む
- 嘔吐、元気消失、食欲不振(腎不全の可能性)
- 主な疾患例
- 腎臓疾患
- 慢性腎臓病(CKD):特に高齢猫に多く、徐々に進行
- 急性腎障害(AKI):中毒、感染、脱水、尿管・尿道閉塞などが原因
- 腎盂腎炎:腎臓まで広がる感染症
- 腎結石・水腎症:尿管の詰まりや尿流の障害
- 膀胱・尿道の疾患
- 膀胱炎(感染性/特発性[猫に多い])
- 膀胱結石・尿道結石(結晶含む)・尿管結石(猫に多い)
- 特発性膀胱炎(猫に多い)
- 尿道閉塞(特に雄猫):命に関わる緊急疾患
- 膀胱腫瘍(移行上皮癌など)
- 前立腺疾患(犬・オス)
- 前立腺肥大(加齢性:未去勢の場合は確実に起こる)
- 前立腺炎、前立腺嚢胞、前立腺腫瘍
- 腎臓疾患
主な検査項目
- 尿検査(比重・pH・蛋白・血尿・沈査)
- 血液検査(BUN・クレアチニン・電解質など)
- 腹部レントゲン・超音波検査(結石・腫瘍など確認)
- 尿路造影検査(造影剤を使って詰まりや形態確認)
- 尿培養・感受性試験(感染性膀胱炎の菌種確認)
主な治療法
- 内科的治療
- 点滴治療(脱水補正)
- 食事療法(腎疾患用、結石予防用)
- 抗生物質、消炎剤、鎮痛薬
- 外科的・処置的治療
- カテーテルによる排尿補助
- 尿道ステント設置(腫瘍性閉塞など)
- 結石摘出手術(膀胱切開、尿道切開)
- 尿管バイパス形成手術(SUBシステムなど)
- 腫瘍の摘出または緩和治療
腎泌尿器科の役割
- 慢性疾患と緊急疾患の両方に対応
- 内科的治療と外科的介入を連携して実施
- 長期的なモニタリングが必要なケースも多く、生活の質(QOL)の維持がカギ
飼い主様に知っておいてほしいこと
- 猫の慢性腎臓病はサイレントキラー:初期症状が少ないため早期発見が大事
- 雄猫の尿道閉塞は緊急対応:放置は命の危険
- 水をよく飲む/おしっこが多いのは腎疾患のサインかも
- 食事療法と定期検査で病気の進行を抑えられることが多い
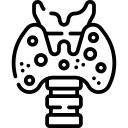
内分泌科
内分泌科は、ホルモンの異常によって引き起こされる病気の診断・治療を専門とする分野です。ホルモンは、体内のさまざまな機能(代謝、成長、繁殖、ストレス反応など)を調整する重要な物質です。
主な対象疾患
- 糖尿病
- 特に犬や猫で多くみられます。
- インスリンの分泌不足や抵抗性により血糖値が高くなる病気。
- 甲状腺疾患
- 犬:甲状腺機能低下症(元気がない、皮膚病、体重増加)
- 猫:甲状腺機能亢進症(食欲はあるが体重減少、活動過多)
- 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
- 犬によくみられる。
- 副腎から過剰にコルチゾールが分泌される。
- 副腎皮質機能低下症(アジソン病)
- コルチゾールやアルドステロンの分泌が不十分。
- 副腎疾患(腫瘍)
- フェレットによくみられる。
- 副腎から過剰に性ホルモンが分泌され、脱毛症やオスでは前立腺肥大による排尿障害がみられる。
- 性ホルモンの異常
- 発情異常、不妊、偽妊娠など。
- 成長ホルモンの異常
- 先天性の成長ホルモン不足、下垂体腫瘍など。
主な診断方法
- 血液検査(ホルモン値測定)
- 視診などによる特徴的な症状
- 尿検査
- 画像診断(超音波、X線、MRIなど)
- ホルモン刺激・抑制試験
治療法
- ホルモン補充(例:インスリン、甲状腺ホルモン)
- ホルモン抑制薬の投与
- 食事療法
- 外科的処置(腫瘍が原因の場合など)
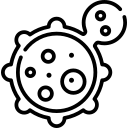
腫瘍科
対象となるできもの
(結節・腫瘤)
- 良性腫瘍(例:脂肪腫、皮脂腺腫など)
- 悪性腫瘍(例:リンパ腫、骨肉腫、乳腺癌、悪性黒色腫など)
- 非腫瘍性病変(例:炎症性肉芽腫、嚢胞、過形成など)
診断方法
- 視診・触診
- 血液検査・生化学検査
- X線、超音波、CT、MRI
- 細胞診(FNA)、組織生検(病理検査)
主な治療法
- 外科手術: 腫瘍を切除
- 化学療法: 抗がん剤の使用
- 放射線治療: 一部の専門施設で実施
- 免疫療法・分子標的療法: 新しい治療法として注目
治療の選択
動物の種類・年齢・腫瘍の種類・ステージ(進行度)・QOL(生活の質)を総合的に考慮し、飼い主様のご意向なども含めてご相談の上で決定します。
飼い主様が知っておきたいこと
- 早期発見がカギ: しこりや行動の変化を見逃さない
- セカンドオピニオンも視野に: 納得できる治療法を探す
- 完治が難しいケースも: 緩和ケアやQOL向上を目指す治療も大切
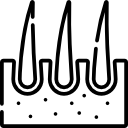
皮膚科
対象となる主な症状・疾患
- 皮膚のかゆみ(アトピー、ノミアレルギー、外部寄生虫など)
- 脱毛(内分泌疾患、感染症、自己免疫疾患)
- 赤み・湿疹(細菌性皮膚炎、真菌感染など)
- フケ・皮膚の厚み(外部寄生虫[ウサギ]、角化異常症など)
- 耳の異常(外耳炎、中耳炎、耳ダニ)
- 皮膚の腫瘍・しこり
- 慢性的な皮膚トラブル
よくみられる疾患の例
| 疾患名 | 特徴 |
|---|---|
| アトピー性皮膚炎 | アレルギーが関与。犬(柴犬)に多く、かゆみ・赤みが出る |
| 膿皮症 | 細菌感染による皮膚炎。かゆみ、脱毛、膿を伴うことも |
| マラセチア皮膚炎 | 酵母菌(マラセチア)による感染症。特有の臭い |
| 疥癬 | ヒゼンダニによる感染症。激しいかゆみ |
| 外耳炎 | 特に垂れ耳やアレルギーの犬に多く、耳垢・臭い・かゆみ |
診断方法
- 視診・触診
- 皮膚掻爬(スクレーピング)(顕微鏡検査)
- アレルギー検査(血液検査)
- 培養検査(細菌・真菌)
- 皮膚の生検(組織をとって病理組織検査)
- ホルモン検査(内分泌疾患を疑う場合) など
治療方法
- 抗菌薬・抗真菌薬(内服・外用)
- ステロイドや免疫抑制剤(アトピーなど)
- 除去食試験(食物アレルギー)
- 定期的な薬浴(シャンプー療法)
- 外用薬や保湿剤によるスキンケア
- 対症療法(かゆみ止め、抗ヒスタミン薬など)
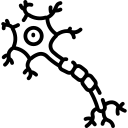
神経科
神経科(神経科・神経内科)は、動物の神経系に関連する病気や異常を診断・治療する専門分野です。神経系とは、脳、脊髄、末梢神経、筋肉を含む全体のネットワークで、体の動きや感覚、意識、行動などをコントロールしています。
神経科の主な対象
- てんかんや発作
- ふらつき、歩行障害
- 首や背中の痛み
- 麻痺(前肢・後肢の動きが悪いなど)
- 意識障害、昏睡状態
- 行動の異常(性格の変化、方向感覚の喪失)
- 顔面神経麻痺や斜頸(首が傾く)
- 脊髄疾患(椎間板ヘルニアなど)
- 神経筋疾患(ミオパチー、重症筋無力症など)
診断に使われる検査
- 神経学的検査(歩き方、反射、痛覚などのチェック)
- MRI・CT検査(脳や脊髄の構造を画像で確認)
- 脳・脊髄液検査(脳や脊髄の炎症や感染を調べる)
- 血液検査・ホルモン検査
- 筋電図(EMG)や神経伝導検査
治療法
- 薬物療法(抗てんかん薬、ステロイド、免疫抑制剤など)
- 外科手術(椎間板ヘルニアの手術など)
- リハビリ・理学療法
- 食事療法やサプリメント(特定の代謝異常に対して)
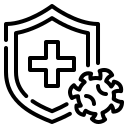
免疫疾患科
主に診る疾患の種類
- 自己免疫性疾患(自己免疫反応)
自分の体を異物と誤認して攻撃してしまう病気 ↓- 免疫介在性溶血性貧血(IMHA)
重度の貧血、黄疸、元気消失など - 免疫介在性血小板減少症(IMTP)
出血斑、鼻血、歯茎出血など - 免疫介在性多発関節炎
関節の腫れ・痛み、発熱、歩行異常など - 天疱瘡、エリテマトーデス(皮膚疾患)
皮膚のただれ、かさぶた、脱毛など - 自己免疫性甲状腺炎(甲状腺機能低下症)
皮膚症状、寒がり、元気低下など
- 免疫介在性溶血性貧血(IMHA)
- アレルギー性疾患(過敏反応)
免疫が過剰に反応してしまうことで発症 ↓- アトピー性皮膚炎(かゆみ、湿疹、脱毛)
- 食物アレルギー(皮膚症状・消化器症状)
- ワクチンアレルギー、薬剤アレルギー
- 蜂・ダニ・植物などに対するアレルギー反応
- 免疫不全・免疫低下
- ウイルス感染による免疫抑制(猫エイズ=FIV、猫白血病=FeLV など)
- 高齢や持病による免疫力低下
主な検査方法
- 血液検査(CBC、生化学、凝固系)
- 自己抗体検査(クームス試験など)
- 骨髄検査(IMHA/IMTPで必要なことも)
- 関節液検査(免疫介在性多発性関節炎)
- 皮膚の生検(免疫介在性皮膚疾患)
- アレルギー検査(血液検査など)
- ウイルス検査(猫FIV・FeLVなど)
主な治療法
- 免疫抑制剤(ステロイド、シクロスポリンなど)
- 支持療法(点滴、輸血、抗生物質、栄養管理など)
- 食事療法(アレルギー・腸炎に対応)
- 環境整備(アレルゲン除去、ストレス軽減)
- 長期的なモニタリング・再発管理
免疫疾患科の特徴
- 診断が難しいことが多く、除外診断や経過観察が必要
- 治療は長期管理が前提(再発しやすいため)
- 他の臓器のトラブルとも密接に関係
- ステロイドなどの薬剤は副作用もあるため、慎重なバランス調整が必要
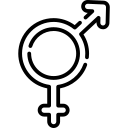
生殖器科
小動物の生殖器科は、生殖器に関する病気の診断・治療・予防、および妊娠・出産のサポートなどを行う獣医療の診療分野です。
主な診療内容
- メス
- 避妊手術(卵巣・子宮の摘出)
- 子宮や卵巣の病気(例:子宮蓄膿症、子宮腫瘍[ウサギ・ハリネズミに多い])
- 妊娠の管理、分娩サポート、帝王切開
- オス
- 去勢手術(精巣の摘出)
- 精巣・前立腺の病気(例:精巣腫瘍、前立腺膿瘍など)
- 潜在精巣(腹腔内や皮下組織の精巣)
- 共通
- 性器の腫瘍・奇形
- 性ホルモン関連の検査や管理
主な検査・処置
- 超音波検査(妊娠や病変の確認)
- 血液・ホルモン検査
- 細胞診
- 外科手術(避妊・去勢、腫瘍摘出、帝王切開など)
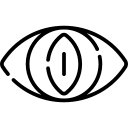
眼科
主な対象部位
- 角膜、結膜、虹彩、瞳孔、水晶体、網膜、視神経など
- まぶたや涙腺も含む
主な眼科疾患
- 外眼部・前眼部
- 結膜炎
- 角膜潰瘍・角膜炎
- 瞬膜突出(チェリーアイ)
- 眼瞼腫瘍・眼瞼内反/外反
- ドライアイ(乾性角結膜炎)
- 眼球内部
- 白内障
- 緑内障(眼圧上昇)
- ぶどう膜炎
- 網膜剥離・変性
- 水晶体脱臼
- その他
- 外傷による眼の損傷
- 先天性奇形
- 視覚障害・失明の原因疾患
主な検査・診断方法
- スリットランプ検査(前眼部の詳細確認)
- 眼圧測定(緑内障などの診断)
- フルオレセイン染色(角膜の傷を確認)
- 涙液量検査(ドライアイの評価)
- 眼底検査・超音波検査
- 網膜の電気生理検査(ERG)(視覚機能評価)
主な治療法
- 点眼薬治療(抗生物質、抗炎症薬、眼圧コントロール薬など)
- 内服薬
- 外科手術(白内障手術、チェリーアイ整復、眼球摘出など)
- 定期的なモニタリング(進行性疾患の場合)
注意が必要な犬種
- シーズー、パグ、フレンチブルドッグ、ペキニーズなどの短頭種は眼が突出しており、角膜損傷や外傷を受けやすい
- 柴犬などは緑内障になりやすい傾向
飼い主様が知っておくと良いこと
- 「目ヤニが多い」「目を細めている」「白く濁っている」「ぶつかりやすい」などは眼科受診のサイン
- 早期の治療で視力の温存が可能なケースも
- 点眼治療は根気強く継続が必要な場合が多い